空調機選定上の重要な項目
空調機自動選定などで得られたデータが、実現可能かどうか精査しなくてはなりません。
冷水循環を使ったシステムの時
冷凍機から送られる冷水の温度を確認してください。 空調機から吹出される冷風は、供給される冷水温度以下には絶対になりません。
従って、自動選定で入力する条件で、吹出し最低温度(下図でポイント2)を10℃としています。
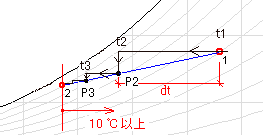
一方、冷却コイルを通過する空気の変化状態は、上図のt1~t2~t3~2の点を移動しながら冷やされていきます。
t1~t2の変化は、絶対湿度が変わらないことから、ドライコイルと呼ばれ冷却コイルの表面近くでの変化です、t2~2の変化は、絶対湿度が下がる除湿が行われ、ウエットコイルと呼ばれています。
この図では、相対湿度が90%の線上を移動していますが、これは冷却コイルの設計条件(C.F-コンタクトファクタ)で変化します。
もし冷却コイル通過する空気が、上図のように10℃以下にならなければ、この空調機では再熱なしで処理できる負荷は、この図のポイント1~2のSHFスロープまでとなります。
もし、このSHFスロープより小さな負荷状態では、たとえ再熱を行っても処理できないことが分かります。(下図のポイント3参照)

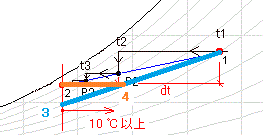
その場合は、更に温度の低いブラインなどの特殊なシステムか、右上の図 ポイント 2 から再熱した空気がポイント 4 が必要になります。しかし、ポイント 4から2 で冷却するためには、相当な送風量が必要になることから、その風量が可能かの検討をする必要が出てきます。
たぶんこの方法は実現が難しいと思われます。 それよりも、システムにドラム式の除湿機を組み合わせるか、負荷自体を見直しSHFを少しでも上げる方法が良いと思われます。
直膨(DX)式のシステムの時
パッケージ式のエアコンの場合、更に空気条件が限定されます。 空調機メーカーの設計範囲が限定されているため、可能な送風空気量の範囲が限定されます。
顕熱が多く発生する部屋の空調機は、標準仕様では対応できない場合が多いと思われます。 その場合、必要送風量から止もうえず、上位ランクの機種を選定する場合がありますが、冷却能力が過大の時、コイル表面で氷結がおこり、空調機を破壊する場合があります。 ただ単純に必要冷却能力で機種を選定すると、思わぬトラブルが発生します。
空調機自動選定で計算された必要送風量よりも大幅に異なる空調機では、基本的な現象は、以下を参考として下さい。
-
十分に負荷処理出来ず、室内の温度にばらつきが大きく出ます。 (風量過少・冷却能力適当)
-
空調機の冷却コイル面の温度が下がり過ぎ、氷結が発生する場合があります。 (風量過少・冷却能力過大)
-
送風量が大き過ぎ、居住空間の換気回数が現実離れしてまう。 (風量過大・冷却能力適当)
最終更新日:2020/02/04
ページ先頭に戻る