自己紹介
私の Web サイトへようこそ! 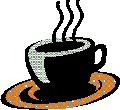
最近のハムライフ
開局当時のコールサインが空きました。 このコールサインを再取得することが出来ることが分かり 早速手続きをしました。
そして JA1PCH が戻ってきました。 「バンザイー」です。
これを機会に、無線機も乗り換え、ヤエスのFTDX3000DとFT991を購入しました。
FTDX3000は、スペクトラムスコープの機能と、CWのデコード機能が使いたくて選びました。
スペクトラムスコープは、回り近所の電波状態が分かるため、込み合っている周波数では有益かもしれませんが、思ったほどでもありませんでした。
.jpg)
FT991はUHF専用のつもりですが 購入してすぐにFT991Aと言う機種が発売され、スペクトラムスコープの機能が充実されてしまい、残念です。
UHFはあまり使わないので、我慢しよう。
ハムライフの歴史
最初にハム免許(無線従事者免許)を取得したのは、昭和38年(1963年)でした。確か高校生のときです。「電話級アマチュア無線技士」という初級免許でした。
無線局を開局したのは、しばらくあとで コールサインは、JA1PCH でした。 アクティブに運用していましたが仕事の都合で、勤務地がシンガポールとなり、以来、約23年間海外勤務となったため、無線局 更新ができず、自動消滅してしまいました。
2006年ようやく勤務地が日本になったため、「カムバック・ハム」として再度開設しました。しかし、従来慣れ親しんだコールサインは、他の人に割り振られて おり、新しいコールサインは「JF1FIV」となりました。
無線機も、ヤエスのFT450S(10W)としたのですがアンテナもホイップアンテナしかないため、さっぱり交信ができませんでした。昔は、ヤエスのFT50というトランシーバーを愛用していましたが、FT450は受信もSN比がいまいちのようです。
従事者免許も、4級(電話級)の初心者クラスでは、ちょっと恥ずかしいため、上級免許を取得することにしました。
最初は講習を受ければ取得できる3級をまず取りました(2010年)。

2級の取得には、苦手なモールス受信試験がありハードルが高かったのですが、1年間計画的に受験勉強をして、平成23年(2011年)にようやく2級に合格することができました。
しかし、2級免許のモールス受信試験は、毎分25文字と非常に遅く、逆に遅すぎて面食らいました。
実際の電信は、まだまだ受信できる自信がありません、毎日特訓中です。
2級に合格したのをきっかけに、無線機もヤエスのFT950(100W)に変えました。FT450に比べて受信感度(SN比)が数段上なので驚いています。
最近のトランシーバーは高価な機械が多数販売されていますが、性能とコストパーフォーマンスを考えると、このFT950はお買い得だと思います、シャックを紹介いたします。


HumRadioDeluxeでシグナルをモニターしています。 とても良くできたソフトです。

UHFは、もっぱらハンディーのトランシーバーで聞いています。
モービル用のホイップアンテナでは不足なため、比較的簡単でオールバンド(3.5~50Mhz)のグランドプレーンに変更しました。
昔のように、4エレメントヤギアンテナを将来の夢としておきます。

昔は、すぐに”CQ~CQ”を出していましたが、じっくり聞くようになりました。
多くの仲間が、”21.420MHz”に集まっており、電波を出すとすぐに交信が出来ましたが、今は静かなこと。
アンテナのせいもあると思いますが、賑わっているのは、7MHzと3.5MHz位のようです。
ハンディーのトランシーバですが、144MHzと435MHz も聞くようになりました。
しかし、特定の仲間間での交信と、モービル同士の交信がほとんどです。心なしか、これらの周波数の交信は、あまりマナーが良くない人が多い様な気がします。
昔は、午前1時くらいから入感するヨーロッパを聞き、明け方から聞こえだすアメリカなどのシグナルが、耳に残っています。
フェージングにつつまれて、とぎれとぎれに入ってくるDXの電波が懐かしいです。
(2013.05.11)
アマチュア無線局の再開
45年以上も前に、熱中していたアマチュア無線を再度始めました。しかし、環境がまったく変わっており、無線機でワッチのみです。
私の場合は、ラジオの組み立てから始まり、自分で製作するのが楽しみでしたが、今は半導体を使ったICチップが主流であり、自作には敷居が高すぎる様です。
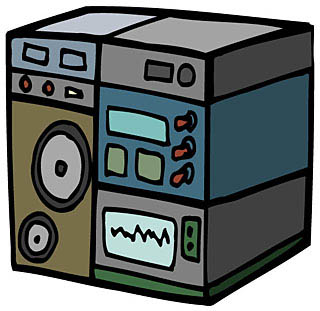
昔は、秋葉原に通っては、パーツを買いあさり、真空管を使ったA3の送信機や受信機作成でしたが、今は当然 半導体でA3J(モガモガ)が大半。
送信周波数も安定度が抜群、こんなの自作では不可能です。またインターネットとハムが合体した通信など、昔では考えられない環境です。
唯一余り変わらないのは、アンテナ製作かな?
短波帯が好きだった私は、アルミのパイプを調達し、21MHZの4エレ八木アンテナを作り、ヨーロッパと良く交信したものです。
学生で小遣いが不足で、アンテナローテータが買えないため、ロープを使い下から回していました、懐かしい限りです。
今は、古典になっていますが、モースル符号を再学習しています。 2010年9月
久しぶりのHP更新
2年間くらいこのHP更新をサボっておりました。
健康の状態が思わしくなく、とうとう退職してしまったのが2007年。
「足を引きずる」ような状態が続きおかしいなと感じ、あるとき散歩をしていて転倒し、かなりいたい思いをしてしまいました。掛かりつけのお医者さんに行くと、精密検査をするべきとの事、早速大学病院に行きました。
以前撮っていた脳のCTスキャンフィルムを持参、病院の面談を受けところ、なんと「即入院」になってしまいました。病名は、水頭症(脳に水が溜まり圧迫の為、障害が起きる病気)であるとの事です。
 入院してからは、原因を確かめる為、毎日検査の連続でした。結果原因が特定できたのが、約1ヶ月半後でした。原因は、脊髄の中に腫瘍が出来、重要な神経を圧迫していました。治療しないでほって置くと、いずれ半身不随になってしまうとの事。 くわばらくわばら。
入院してからは、原因を確かめる為、毎日検査の連続でした。結果原因が特定できたのが、約1ヶ月半後でした。原因は、脊髄の中に腫瘍が出来、重要な神経を圧迫していました。治療しないでほって置くと、いずれ半身不随になってしまうとの事。 くわばらくわばら。
脳髄で作られる髄液にタンパクが下り、どろどろの髄液が脳まで来るため、水頭症になったようです。腫瘍の摘出手術を受けたのが、2008年12月、ほんとに長い手術だったそうです。(本人は覚えていません)
幸い、腫瘍は良性であったため、摘出すれば回復するそうです。非常に珍しい病気であったようです。
手術後、半年くらいリハビリで近所を歩きまわっていましたが、無性にパソコンをいじりたくなり今では、毎日が楽しいパソコンライフとなりました。たぶん、脳も回復してきたようです。 2009年9月
日本で約12年、シンガポールに来て早や20年以上、建築設備設計や工事に携わってきました。
大規模な設計プログラムはいろいろとありますが、扱いが煩雑であったりして現状では概算設計的なものが多すぎます。実務を通し、何とか早く正確なアクションができないものかと試行錯誤してきました。
そこで、みようみまねで設計シミュレーションのプログラムを書き出しました。最初は、BASIC言語 ・C言語でDOSベースでしたがウインドウが主流になり 、お蔵入りしていた昔のプログラムを、最近やっとウインドウベースに書き換え実用的なプログラムが部分的に出来ました。
まだ不足や・バグがあると思いますが発表したいと 、このホームページを立ち上げました。技術的なアドバイスや提案、さらに共同でより 良いものに出来れば幸いです、フィードバックのフォームでどしどしご意見をお聞かせください。
パソコン暦
最初にコンピュータらしきものを触ったのは、1977年にシャープのポケコンを買ってBasicなるものを初めて使いました。1年も経たないうちに、どうしても本格的なパソコンが欲しくてNEC8800を購入しました。モニターは白黒、データのレコードは、専用のカセットレコーダーという組み合わせでした。
ここで紹介している補間式のプログラム(MFI)はこの時BASICで原型を作りました。それから、NEC9801のF3モデル(初めてハードディスクが付属したモデルを発売と同時にすぐ購入し、ハードディスクのスピードの速さに魅了させられました、当時のハードディスクの容量はわずか10MBでしたが。
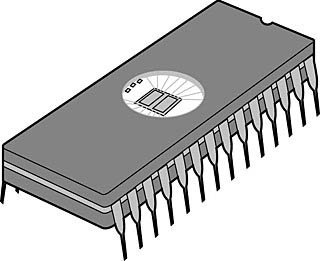
この時、初めてMS-DOSとBASICコンパイラを導入し、配管抵抗計算プログラムなどを作りました。すぐに飽き足らなく、NEC98VXを購入したころ勤務地がシンガポールになり、MS-DOSも英語バージョンになりました。
当時シンガポールではIBMコンパチが一般的で、NECと金額を比較するとめちゃくちゃ安く、それ以来IBMコンパチにお世話になっています。このころから数えるとおおよそ15台以上のパソコンをとっかえひっかえ変えました。
自作のパソコンに興味を惹かれ、ハードデスクだけでもSCSIやIDEを含め10台以上購入して遊んでいました。最近は、パソコンの性能が極端に速くなり 買い換えても通常の作業ではあまり変わらないため、新しい機械に換える欲望はなくなりました。
OSは、 MS-DOS/IBM-DOSから、WIN3.1, WIN95, WIN98, WIN2000, WINXP と変わったのですが、WIN2000が
一番安定しているので、現在はWIN2000を使っています。WIN XPを使ってみたのですが、スキャナーやADSLモデムのドライバ相性が悪いため使っていません。
プログラム暦
先にも書きましたが、シャープのDOSから始まり、NEC 98BASIC、MS-DOSのBASICコンパイラまではBASICが主体でしたが、C言語に興味が移りTurbo Cに乗り換え、この時点でここに紹介している大半のプログラムの原型を作りました。
そのうち、C++がリリースされBorlandのC++を使い出したのですが、オブジェクト指向が良く分からず、ほとんどCで書いていました。Windowsのプログラムに当然興味を持ちましたが難しく、プログラミングからしばし遠ざかっていました。
たまたま日本に1時帰国した時に、VC5を手に入れ再度チャレンジしだしました。最初にC言語を始めた時、あまりにもBASICと違い、一番苦労したのはBASICライクな入力をする為のEditルーチンでした。
半年かけて、みようみまねで作りましたが、それからは比較的簡単にプログラムを書くことが出来ました。これを思い出し、難解なWindowsに再度チャレンジしましたが、運良く息子がプログラムの本職になったこともあり手助けしてもらい現在にいたっております。
しかし、痒いところに手が届かなく、山ほど参考書を買ってみたのですが、書いてある内容がなかなか理解できずコーディングには自身がありません、50歳の手習いは限界がありそうです。
やりたい事は、山ほどあるのですが1つのプログラムに10年も掛かってしまったのでは。。。。。
しかし、空調負荷計算は実務ですごく重宝しています。
ページ先頭に戻る
