小規模冷蔵庫の湿度
温度より湿度が重要なとき
ある大手の総合病院の大規模改修工事に携わったときのことです。
医薬品を管理している病院の担当者から、薬品貯蔵している冷蔵庫の「湿度が高くて困る」とのクレームが入りました。この冷蔵庫は、私が設計したものではなく、詳細が不明でしたので現地確認に出向きました。
規模は、15㎡程の小さなもので、天井吊りのユニットクーラーが1台、外部にR12冷媒を使ったコンデンユニットが設置されていました。壁は、冷蔵庫専用の断熱パネルで構成されていました。
理想的には、庫内温度が7~10℃で湿度を50%RH位に保たないと、カビの繁殖が抑えられないとのことですが、現状は温度は問題ないのですが、湿度が90%前後の値を示しているようでした。
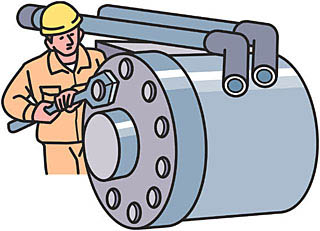
ドラム式の自記温湿度計を設置し監視を続けたました。冷蔵庫の熱負荷計算が良く分からず、正確に判断出来なかったのですが、冷凍機が運転し始めると、庫内温度はすぐに下降し冷凍機はアイドル状態になっていました。従って、冷凍機の容量は十分すぎるように思いました。
設計施工した経緯を調べると、突貫工事で時間がなかった為、床面積の情報のみで、冷蔵庫施工業者に依頼したようです。冷凍業者も、大は小を兼ねると、大き目の冷凍機を設置したようです。
そこで、病院側に以下の提案をして実験を行う事にしました。
ユニットクーラ吹出部分に仮設再熱ヒータを取り付ける。
数日間この状態で温湿度をモニターする。
湿度が下がることを確認できたら、本設の再熱ヒータを取り付ける
実験の結果、みるみる湿度は下がりすぎる程に下がりました。
そこで、本設として自動制御の為の湿度センサーを追加しました。当時は、まだサイリスターの様な、無段階制御が出来る素子がなかったので、ステップコントローラとリレーを使った制御回路を設計し、追加しました。
後日、空気線図を使い技術的に解析しましたが、適切な冷凍能力と送風量が如何に大切かが判った次第です。現在は、送風空気量も自動で制御できるし、ヒータの再熱の無段制御できるし、いろいろなバラエティーにとんだシステムが組めるはずです。特に、可変風量システムを上手に使えば、不要な再熱などを抑制し、省エネのシステムが組めるはずです。
これらの問題は、40年以上前の出来事です。(10/09/13)
ページ先頭に戻る